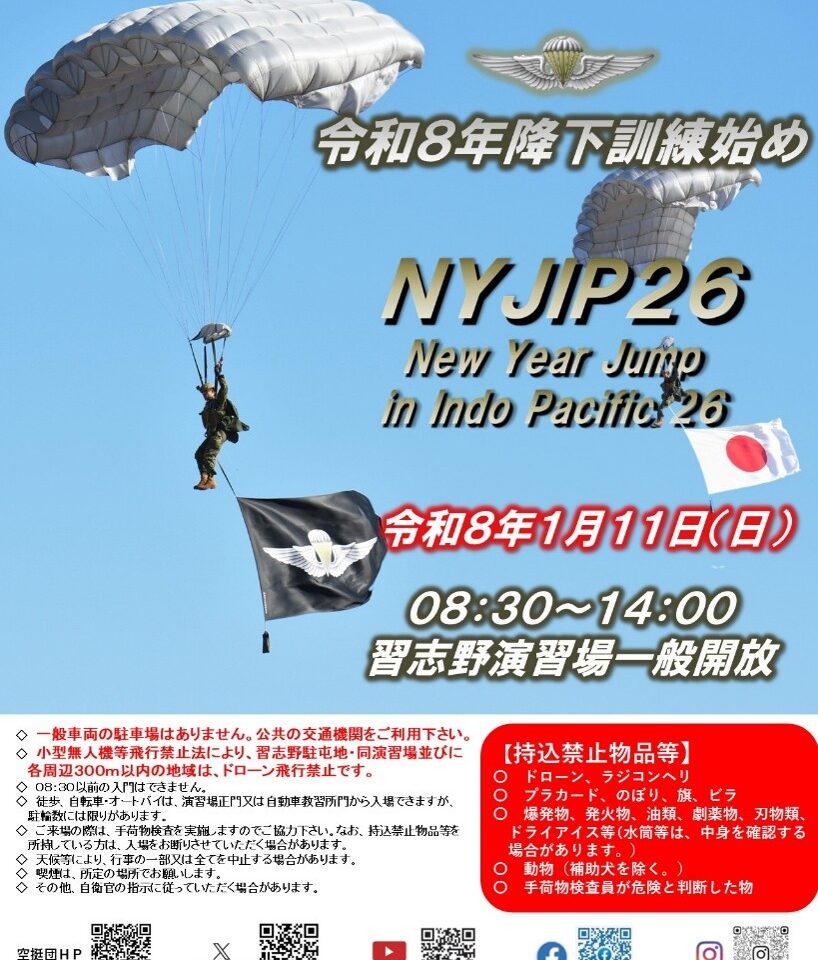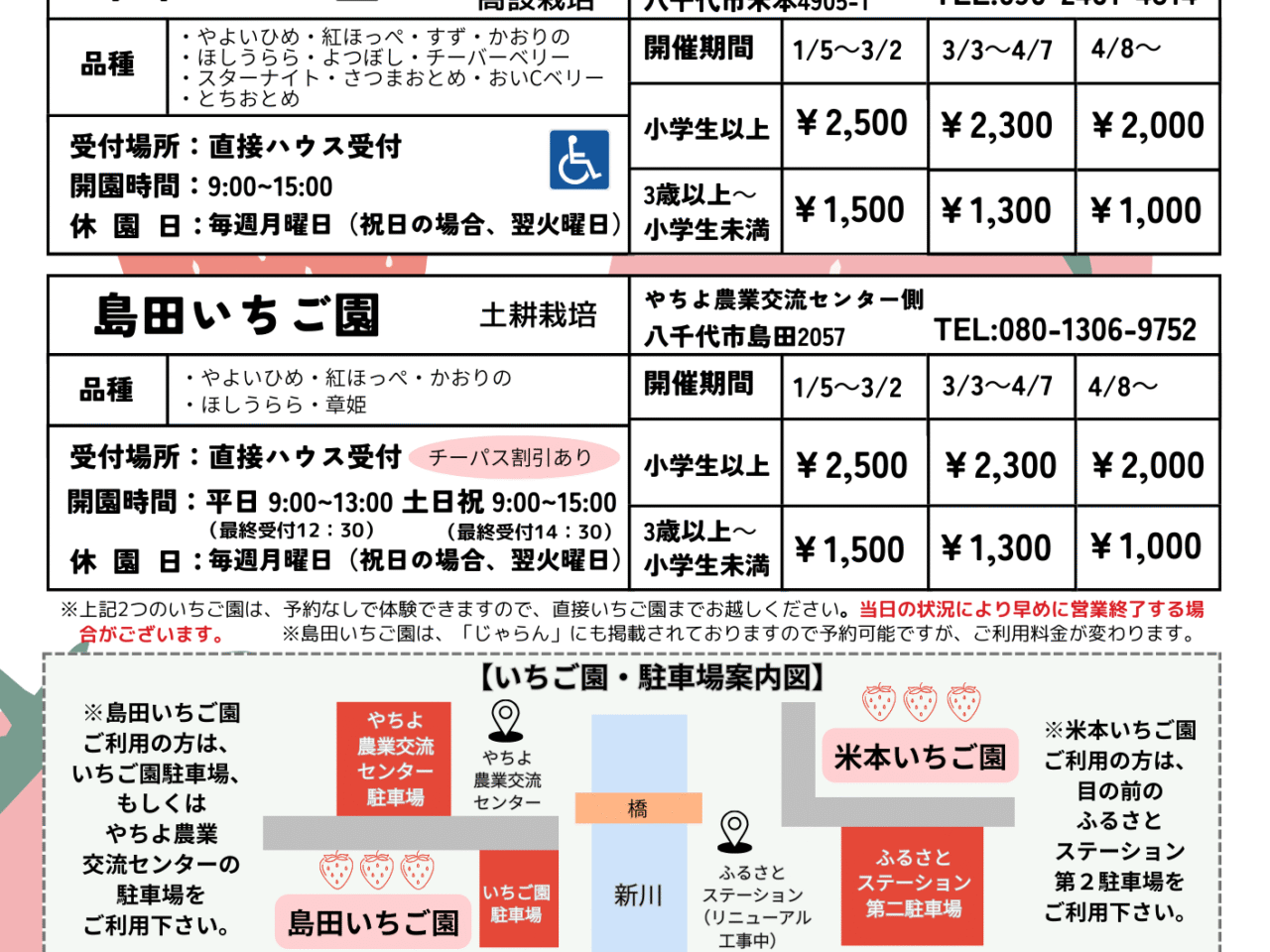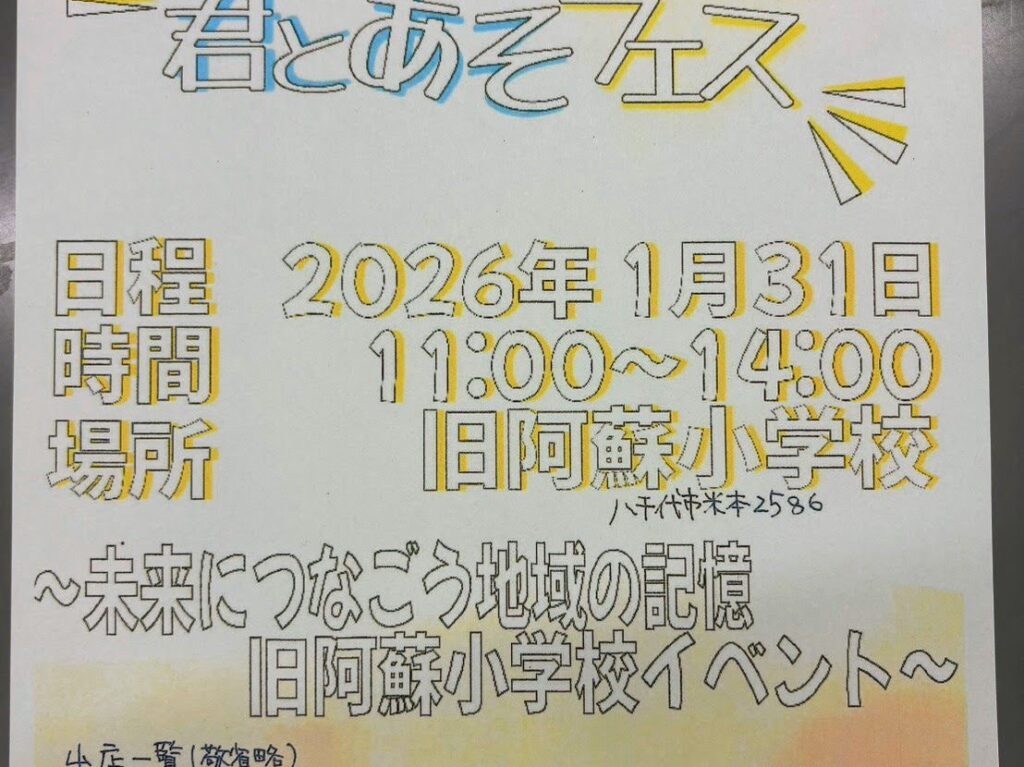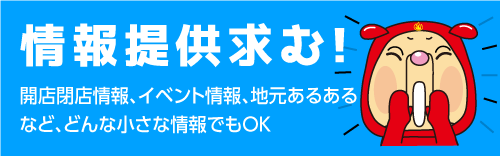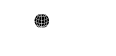【習志野市】事故からの早期救出!習志野市消防本部が若手隊員に向けて車両破壊訓練を実施
2025年1月27日、習志野市消防訓練センター敷地内において、交通事故での閉じ込め事案を想定した訓練が実施されました。この訓練は、勤務年数2年未満の若手隊員を中心に、車両破壊を中心とした内容で行われました。

交通事故で車が大きく壊れてしまうと、ドアが開かなくなったり、車内に人が閉じ込められたりするケースがあります。そんな時、一刻も早く救出するために、消防隊員は車両を破壊して救助活動を行います。

今回の訓練では、建設機械を取り扱うメーカー・(株)オグラさんから解体に使用する資機材と、習志野市内で創業60周年を迎えた自動車整備・(有)杉田モータースさんから車両の提供を得て、今回は実際に一台まるまる破壊。普段の訓練ではなかなか経験できないシチュエーションを、2社の提供を受けて実現する事ができたんだそう。

訓練は、資機材の取り扱い説明の後、解体作業を開始。まずは強化ガラスの破壊から。飛散防止のガムテープ貼りは、時間と効率を考慮しつつ、強化ガラスの性質を理解した上で最も効果的な方法で行う必要があります。訓練ではその最適な方法を学びました。
フロント・サイド・バック全ての窓ガラスを破壊したら、次はドアの取り外しです。

どういう作業を行うと、どのようなねじれや反発が起きるかを実際に体感しながら、取り外し作業を進めます。

全てのドアが外されました。次は後部のバックドアです。

この車はガソリン車ですが、実際に取り扱うのが電気自動車の場合もあります。電気自動車の場合は車のフロント部分に電子系統の配線が集中しており、床面にはバッテリーが敷かれています。よって感電のリスクを避けながら開口部を作るとしたら、バックドアが一番安全なんだそう。耐電手袋も必須です。

バックドア部分を跳ね上げるのではなく、このように下にせり出させ、板などを配置する事で人命救助の際の通路として確保もできます。

資機材の特製や、車両の板金の部位による性質の違いを知る事ができ、解体箇所によって資機材使い分け、刃の当て方なども変えていく事の合理性や重要性など、見ているだけでもとても勉強になりました。

参加した隊員たちは、車両の構造や破壊方法、救助資機材の扱い方を習得しました。人命救助のため、安全かつ迅速に救出する方法をより確実なものとしたようです。もしもの事故の際にも、迅速かつ的確な救助活動ができるよう、訓練後も各個人でさらにブラッシュアップに励んでいるとのことです。
習志野市消防本部では、今回の訓練成果を活かして、これからも市民の安全・安心を守っていくとのこと。私たちも、交通事故に気を付けて、安全な毎日を過ごしたいですね。

そしてもし、事故現場に遭遇したら、まずは自分の安全を確保して、119番通報をお願いします。
「習志野市消防訓練センター」はこちら。